�����p�ʼn����Ɏc���ꂽ�O�Ԑ����t�B�[���h�ɁA���R���������ɖ�����ł��܂��B�@
�O�Ԑ��������}��ZUKAN
�O�Ԑ����������ڂ�b
�@�^�C�����K�U�~�@�@���A�x����������
 �@����L�����40cm�����^�̃J�j�B�I�X�̓L���C�ȐF�̑̂����Ă���i���X�͔��ΐF�Œn���j�B
�^�C�����Ƃ������O�́u�g�����M�ш�v���Ӗ����A�O����ł͂Ȃ��B���i�͋��\�ŁA�n�T�~�̗͂͋����A�L�������ĐH�ׂ邱�Ƃ��B
�܂���Ԍ��̑����肱���{�[�g�̃I�[���̂悤�ɂȂ��Ă���A�j�����Ƃ��ł���B
�̂͂ǂ��ł���������Ƃꂽ���������A���ݎO�Ԑ��ł͂��܂Ɍ���������x�B�Ǘ��l���V�[�Y���ɂȂ�ƂƂ�ɍs�����A��ӂɈ�C�Ƃ��Ηǂ������B
���͔��ɗǂ��A�l�I�ɂ̓P�K�j������̂ł͂Ǝv���i�����I�Ɩ��X�`���I�X�X���j�B�J�j�͎��ʂƈ�C�ɖ��������Ȃ�̂Ő��������̂����B
�@����L�����40cm�����^�̃J�j�B�I�X�̓L���C�ȐF�̑̂����Ă���i���X�͔��ΐF�Œn���j�B
�^�C�����Ƃ������O�́u�g�����M�ш�v���Ӗ����A�O����ł͂Ȃ��B���i�͋��\�ŁA�n�T�~�̗͂͋����A�L�������ĐH�ׂ邱�Ƃ��B
�܂���Ԍ��̑����肱���{�[�g�̃I�[���̂悤�ɂȂ��Ă���A�j�����Ƃ��ł���B
�̂͂ǂ��ł���������Ƃꂽ���������A���ݎO�Ԑ��ł͂��܂Ɍ���������x�B�Ǘ��l���V�[�Y���ɂȂ�ƂƂ�ɍs�����A��ӂɈ�C�Ƃ��Ηǂ������B
���͔��ɗǂ��A�l�I�ɂ̓P�K�j������̂ł͂Ǝv���i�����I�Ɩ��X�`���I�X�X���j�B�J�j�͎��ʂƈ�C�ɖ��������Ȃ�̂Ő��������̂����B
�@�`�`�u�@�@���A�x����������
 �@�^�t�ȋ��B���̉���ɔ��ɋ����A���ɐ����̊������Ă��Ō�܂Ő����c��B�G�H���ŐH�~�����A������菬���Ȑ����͂ǂ�ǂ�H�ׂ�B
�܂��꒣��ӎ������������������ߑ��̐����Ǝ����̂���ς��Ǝv������A���̐����ł͏�肭����Ă���l�q�B
�I�X�������Ǝq��Ă�����Ƃ����C�N�������Ղ���������킹�Ă���B�ꌩ����ƒn�������A�悭����ƃq�����������B
�@�^�t�ȋ��B���̉���ɔ��ɋ����A���ɐ����̊������Ă��Ō�܂Ő����c��B�G�H���ŐH�~�����A������菬���Ȑ����͂ǂ�ǂ�H�ׂ�B
�܂��꒣��ӎ������������������ߑ��̐����Ǝ����̂���ς��Ǝv������A���̐����ł͏�肭����Ă���l�q�B
�I�X�������Ǝq��Ă�����Ƃ����C�N�������Ղ���������킹�Ă���B�ꌩ����ƒn�������A�悭����ƃq�����������B
�@�n�[�ނ�̊O���Ƃ��āu�_�{�n�[�v�ƌ����鋛�i�_�{�n�[�Ƃ������͂��Ȃ��j�B �O�Ԑ��⋫��ł͂悭�������鋛�ŁA�n��ɂ���Ă͐H�p�Ƃ��邻�����B
�@�g�T�J�M���|�@�@���A�x����������
 �@�����܂Ƀg�T�J������̂ŁA�g�T�J�M���|�B�Ȃ�̂��߂Ƀg�T�J������̂��̓C�}�C�`�킩��Ȃ��B
�s�����������Ă���A���܂��ƌ����o�邱�Ƃ��B�����ꏊ�ɉB���̂��D���ŁA�C�ł̓J�L�̊L�k�̒��ɂ��邱�Ƃ������B
����ȏK������߂܂���̂ɂ͋�J����B
�@�����܂Ƀg�T�J������̂ŁA�g�T�J�M���|�B�Ȃ�̂��߂Ƀg�T�J������̂��̓C�}�C�`�킩��Ȃ��B
�s�����������Ă���A���܂��ƌ����o�邱�Ƃ��B�����ꏊ�ɉB���̂��D���ŁA�C�ł̓J�L�̊L�k�̒��ɂ��邱�Ƃ������B
����ȏK������߂܂���̂ɂ͋�J����B
�@���Ƀ^�t�ȋ��Ő��̂Ȃ��ꏊ�ł����炭�����Ă�����悤���B
�Ƃ����̂��A���̐����̃g�T�J�M���|�͋��삪�Ԓ��Ő^���ԂɂȂ����Ƃ��ɁA��݂̃R���N���[�g�̏�ɑł��グ���Ă������́B
�߂܂����Ƃ��͊�����тĂ����_�����Ǝv�������A���������Ă��ƌ��C�ɉj���o�����B
�@�}�i�}�R�@�@���A�x����������
 �@�݂Ȃ��H�ׂĂ���i�}�R�͂���B��{�I�Ƀi�}�R�̓��ɂ͓ł����邪�A���̃}�i�}�R�͓ł̗ʂ����ɏ��Ȃ����ߐ��ŐH�ׂ���B
�i�}�R�Ƃ����͕̂s�v�c�Ȑ������ŁA�ڂ��Ȃ���A�S�����Ȃ��B������̌����琅���z���Čċz�����������B
�̂ɂ���u�c�u�c�́u���ڑ��v�Ƃ������A���̖����͂킩���Ă��Ȃ��i�{���̑��͂������ɂ�������j�B
�H���͍��̒��̗L�@�������ƈꏏ�ɐH�ׁA���������Ƃ��ďo���B�Ȃ̂ł����������ɂ���ƍ����L���C�ɂ��Ă����B
�܂��}�i�}�R�͐������Ⴂ�������C�ŁA�Ă̏����Ƃ��ɂ͏������Ȃ��Ċ�̊ԂȂǂɓ��蓮���Ȃ��Ȃ�i������u�Ė��v�Ƃ����j�B
�͎̂O�Ԑ��ł��悭�����������������A�ŋ߂͂ƂĂ����Ȃ��Ȃ����炵���B�Ǘ��l���P�x�����߂܂������Ƃ��Ȃ��B
�@�݂Ȃ��H�ׂĂ���i�}�R�͂���B��{�I�Ƀi�}�R�̓��ɂ͓ł����邪�A���̃}�i�}�R�͓ł̗ʂ����ɏ��Ȃ����ߐ��ŐH�ׂ���B
�i�}�R�Ƃ����͕̂s�v�c�Ȑ������ŁA�ڂ��Ȃ���A�S�����Ȃ��B������̌����琅���z���Čċz�����������B
�̂ɂ���u�c�u�c�́u���ڑ��v�Ƃ������A���̖����͂킩���Ă��Ȃ��i�{���̑��͂������ɂ�������j�B
�H���͍��̒��̗L�@�������ƈꏏ�ɐH�ׁA���������Ƃ��ďo���B�Ȃ̂ł����������ɂ���ƍ����L���C�ɂ��Ă����B
�܂��}�i�}�R�͐������Ⴂ�������C�ŁA�Ă̏����Ƃ��ɂ͏������Ȃ��Ċ�̊ԂȂǂɓ��蓮���Ȃ��Ȃ�i������u�Ė��v�Ƃ����j�B
�͎̂O�Ԑ��ł��悭�����������������A�ŋ߂͂ƂĂ����Ȃ��Ȃ����炵���B�Ǘ��l���P�x�����߂܂������Ƃ��Ȃ��B
�@�N���_�C�@�@���A�x����������
 �@�ނ�l����D���ȋ����̇@�B�傫�ȃN���_�C��ނ邽�߂ɐl���������Ă���I�W�T���͒������Ȃ��B
�H�~�����Ő����������A���̐����ɘA��Ă��Ă��甼�N���炸�ő̂̑傫����4�`5�{�ɂȂ��Ă��܂����B
60cm���炢�܂Ő�������B�Ȃ�ł��H�ׂ鈫�H�Ƃ��ėL���ŁA�����ȋ���G�r�A�J�j�A�C���A�ʂĂ̓X�C�J�◬��Ă����S�~���H�ׂ邻���ȁB
����ȏK������ߔN���A�[�t�B�b�V���O�̑Ώۋ��Ƃ��Đl�C�������B�܂����i�͑@�ׂ���_�ƌ����A
��������ɕq���ɔ������邩�Ǝv���A�т����肷�邮�炢�ꏊ���䂤�䂤�Ɖj���ł��邱�Ƃ��B
�@�ނ�l����D���ȋ����̇@�B�傫�ȃN���_�C��ނ邽�߂ɐl���������Ă���I�W�T���͒������Ȃ��B
�H�~�����Ő����������A���̐����ɘA��Ă��Ă��甼�N���炸�ő̂̑傫����4�`5�{�ɂȂ��Ă��܂����B
60cm���炢�܂Ő�������B�Ȃ�ł��H�ׂ鈫�H�Ƃ��ėL���ŁA�����ȋ���G�r�A�J�j�A�C���A�ʂĂ̓X�C�J�◬��Ă����S�~���H�ׂ邻���ȁB
����ȏK������ߔN���A�[�t�B�b�V���O�̑Ώۋ��Ƃ��Đl�C�������B�܂����i�͑@�ׂ���_�ƌ����A
��������ɕq���ɔ������邩�Ǝv���A�т����肷�邮�炢�ꏊ���䂤�䂤�Ɖj���ł��邱�Ƃ��B
�@���ɂ��Ă͕]����������鋛�ʼn��i�������B�������ɃL���C�Ȉ����i����j�œ˂������̂̓}�_�C�ɕ����ʔ��������������A
10���ɉY���Œނ����̂̓I�V�b�R�̂悤�ȏL���������B
�@�}�n�[�@�@���A�x����������
 �@���ɐ������������ŁA�t��ɐ��܂ꂽ1�`2mm�̒t����9�`10���ɂ�10cm�ȏ�ɐ�������B
�~�ɂȂ�Ǝ���ɐ[��ւƈړ����Y�����邪�A���̂Ƃ��ɐ����[�g���ɂ��Ȃ�g���l�����@���Ă����ɗ����Y�ݕt����B
���̐��b�̓I�X���s���B���E�̓C�N�����������B�����͖�1�N�ŁA�܂��2�N�قǐ�������̂�����B
�D������Ɏ����킸�A���i�͂��U���I�ŁA��������ƃ��h�J�������˂�����A�����ȋ���߂܂��ĐH�ׂ邱�Ƃ�����B
���̐��i���Z�������̂Ȃ��őf�����������邽�߂Ȃ̂�������Ȃ��B
�@���ɐ������������ŁA�t��ɐ��܂ꂽ1�`2mm�̒t����9�`10���ɂ�10cm�ȏ�ɐ�������B
�~�ɂȂ�Ǝ���ɐ[��ւƈړ����Y�����邪�A���̂Ƃ��ɐ����[�g���ɂ��Ȃ�g���l�����@���Ă����ɗ����Y�ݕt����B
���̐��b�̓I�X���s���B���E�̓C�N�����������B�����͖�1�N�ŁA�܂��2�N�قǐ�������̂�����B
�D������Ɏ����킸�A���i�͂��U���I�ŁA��������ƃ��h�J�������˂�����A�����ȋ���߂܂��ĐH�ׂ邱�Ƃ�����B
���̐��i���Z�������̂Ȃ��őf�����������邽�߂Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�ȒP�ɒނ�鋛�����A���͍������B�V�Ղ�p�Ƃ��Ď�������}�n�[�͂��Ȃ�̒l�i�炵���B�h�g����i�Ƃ̃E���T�B
�܂����̋߂��̋���̓n�[���悭�ނ�邱�ƂŗL���B
�@�R�u���R�o�T�~�@�@���A�x����������
 �@�@���肱�Ԃ����炢�ɂȂ���ɑ傫�ȃ��h�J���B
�n�T�~�����E�ɊJ�����Ƃ���u���R�o�T�~�v�Ƃ����炵�����A�Ǘ��l�ɂ͑��̃��h�J���Ƃ̈Ⴂ���悭�킩��Ȃ������B
��Ȃǂɐ������R�P�����������H�ׂĂ����B�����͒x���A���i�����₩�B
�E�炵���k���A�����Ă���p�ɂ�������Ȃ��߁A�����������Ǝ��̂��Ǝv���ăq���b�Ƃ���B
�ŋ߂̓����p���h�J���ƊE�S�̂Ɍ����邱�Ƃ����A�Z�݂��ƂȂ�L�k���s�����Ă���炵���B
���̂��ߌ����������芄�ꂽ�肵���s�Ǖ����ɓ������Ă��郄�h�J�������Ȃ��Ȃ��B
�c�����R�u���R�o�T�~�����ꂻ���ȊL�k���������̕������܂�����A�����Ɛ����̏�Ȃǂɒu���Ƃ��Ē�����Ə�����܂��B
�i�������F��j�X���h���Ă���L�k�͕s�Ƃ����Ă��������B)�@
�@�@���肱�Ԃ����炢�ɂȂ���ɑ傫�ȃ��h�J���B
�n�T�~�����E�ɊJ�����Ƃ���u���R�o�T�~�v�Ƃ����炵�����A�Ǘ��l�ɂ͑��̃��h�J���Ƃ̈Ⴂ���悭�킩��Ȃ������B
��Ȃǂɐ������R�P�����������H�ׂĂ����B�����͒x���A���i�����₩�B
�E�炵���k���A�����Ă���p�ɂ�������Ȃ��߁A�����������Ǝ��̂��Ǝv���ăq���b�Ƃ���B
�ŋ߂̓����p���h�J���ƊE�S�̂Ɍ����邱�Ƃ����A�Z�݂��ƂȂ�L�k���s�����Ă���炵���B
���̂��ߌ����������芄�ꂽ�肵���s�Ǖ����ɓ������Ă��郄�h�J�������Ȃ��Ȃ��B
�c�����R�u���R�o�T�~�����ꂻ���ȊL�k���������̕������܂�����A�����Ɛ����̏�Ȃǂɒu���Ƃ��Ē�����Ə�����܂��B
�i�������F��j�X���h���Ă���L�k�͕s�Ƃ����Ă��������B)�@
�@�i�x�J�@�@���A�x����������
 �@�O�Ԑ��ł͋M�d�ȃJ���t���ȋ��B�^�C���\�X�t�@���ɂ͂��܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�悭����Ɩڋʂ܂ŃV�}�͗l�ɂȂ��Ă���B
����͊O�G����ڂ̈ʒu�����܂������߂��낤���H�Ȃ��u�i�x�J�v�Ƃ����̂��͓�ł���B
�Ȃ��ӎ������ɋ����A�܂��P�C�̂Ȃ������Ȃ�L���̂ŁA�����C�������Ƃ��ƂĂ�����B
�Ǘ��l�̂��C�ɓ���̋��̂P�ŁA������߂܂��邽�߂ɋ���ɂ��������ʂ��A�傫�ȃ^���Ԃ������Ċݕǂ��牽�x���������̂��������ʁA���ɂɂȂ��Ă��܂����B
�@�O�Ԑ��ł͋M�d�ȃJ���t���ȋ��B�^�C���\�X�t�@���ɂ͂��܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�悭����Ɩڋʂ܂ŃV�}�͗l�ɂȂ��Ă���B
����͊O�G����ڂ̈ʒu�����܂������߂��낤���H�Ȃ��u�i�x�J�v�Ƃ����̂��͓�ł���B
�Ȃ��ӎ������ɋ����A�܂��P�C�̂Ȃ������Ȃ�L���̂ŁA�����C�������Ƃ��ƂĂ�����B
�Ǘ��l�̂��C�ɓ���̋��̂P�ŁA������߂܂��邽�߂ɋ���ɂ��������ʂ��A�傫�ȃ^���Ԃ������Ċݕǂ��牽�x���������̂��������ʁA���ɂɂȂ��Ă��܂����B
�@ ��ɋ�����J�L�̊L�k�ɉB���̂���D���ŁA��������炾���Ђ傱���Əo���p�͈��炵���B ���̗l�q���`���A�i�S�Ɏ��Ă���ƌ����l�����邪�A�`���A�i�S�Ƃ͑S���̖��W�B
�@���W�i�@�@���A�x����������
 �@�ʏ́u�O���v�B�ނ�l����D���ȋ����̂Q�B���{�ł͂��̋���ނ邽�߂ɂ��������̒ނ����ݏo����A�Ƃ�ł��Ȃ��z�̂������g���Ă���B
���i�͂ǂ�~�������a�œ����ǂ��A�Ȃ��Ȃ��l�Ԃ��ߊ�点�Ă���Ȃ��B���W�i�ɂ́u�C�W���v�Ƃ�������������B
���W�i�͂P�C�Ŏ����Ɖ䂪����ő��̋����U�����A���C���Ŏ����ƒ��Ԃ͂���̃��W�i������Ă݂�Ȃł������C�W����Ƃ������Ƃ��悭�N����B
�������C�̒��ł͐��C�`���\�C���Q����Ȃ��Ē��ǂ��j���ł���A�����Ƃ�������Ԃɓ����ƁA��ɏ������C�W������������̂��B
����͉����l�ԎЉ�ɒʂ���Ƃ��낪����̂�������Ȃ��B���̂��Ƃɂ��Č��y�����u�����ȃN���v�̋L�������Гǂ�ł݂Ăق����B
�c���������̐����̃��W�i�͂T�C�Œ��ǂ�����Ă���c�s�v�c���B
�@�ʏ́u�O���v�B�ނ�l����D���ȋ����̂Q�B���{�ł͂��̋���ނ邽�߂ɂ��������̒ނ����ݏo����A�Ƃ�ł��Ȃ��z�̂������g���Ă���B
���i�͂ǂ�~�������a�œ����ǂ��A�Ȃ��Ȃ��l�Ԃ��ߊ�点�Ă���Ȃ��B���W�i�ɂ́u�C�W���v�Ƃ�������������B
���W�i�͂P�C�Ŏ����Ɖ䂪����ő��̋����U�����A���C���Ŏ����ƒ��Ԃ͂���̃��W�i������Ă݂�Ȃł������C�W����Ƃ������Ƃ��悭�N����B
�������C�̒��ł͐��C�`���\�C���Q����Ȃ��Ē��ǂ��j���ł���A�����Ƃ�������Ԃɓ����ƁA��ɏ������C�W������������̂��B
����͉����l�ԎЉ�ɒʂ���Ƃ��낪����̂�������Ȃ��B���̂��Ƃɂ��Č��y�����u�����ȃN���v�̋L�������Гǂ�ł݂Ăق����B
�c���������̐����̃��W�i�͂T�C�Œ��ǂ�����Ă���c�s�v�c���B
�@�C�_�e���M���|�@�@���A�x����������
 �@�C���f�����ړ����邱�Ƃ���u��ʓV�i�����Ă�j�v�̖��O�������炵���B
�㉺�̃A�S�ɋ��͂ȉ�������Ă��芚�܂��Ɣ��ɒɂ��B�n�[�ނ�̊O���Ƃ��Ēނ�邱�Ƃ�����̂ŋC�����悤�B
�Â��̐F�ɉ����A������̊Ԃ�L�k�ɉB��Ă���̂ŁA�����̂Ȃ��ł��Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B
�����Ă��Ă��u���A�������������ȁv�ƂȂ肪���B�n���ł���B
2019�N�A��̓h���}�̃^�C�g���ɂ��Ȃ����̂ŁA�����̒m���x���オ�邩������Ȃ��i�c�オ��Ȃ����j�B
�@�C���f�����ړ����邱�Ƃ���u��ʓV�i�����Ă�j�v�̖��O�������炵���B
�㉺�̃A�S�ɋ��͂ȉ�������Ă��芚�܂��Ɣ��ɒɂ��B�n�[�ނ�̊O���Ƃ��Ēނ�邱�Ƃ�����̂ŋC�����悤�B
�Â��̐F�ɉ����A������̊Ԃ�L�k�ɉB��Ă���̂ŁA�����̂Ȃ��ł��Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B
�����Ă��Ă��u���A�������������ȁv�ƂȂ肪���B�n���ł���B
2019�N�A��̓h���}�̃^�C�g���ɂ��Ȃ����̂ŁA�����̒m���x���オ�邩������Ȃ��i�c�オ��Ȃ����j�B
�@���r�i�K�z�����h�J���@�@���A�x����������
 �@���{�S�����낢��ȏꏊ�ɐ������郄�h�J���B���̐�[�̊߁i�l�Ԃł����Ƒ��̎w�ɂ����镔���j�������̂Łu���r�i�K�v�̖��O�������B
�O�Ԑ��́u���̏o�Ђ����v�ɂ͑�ʂ̃��r�i�K�z�����h�J������炵�Ă���A�����ɗ��肢���ς��ɏW�߂邱�Ƃ��ł���B
�܂����̒��ɓ���Ȃ��Ă���݂̏�ɂ�������̂ŁA�����Ȏq���ł��ȒP�ɕ߂܂��邱�Ƃ��ł���B
�@���{�S�����낢��ȏꏊ�ɐ������郄�h�J���B���̐�[�̊߁i�l�Ԃł����Ƒ��̎w�ɂ����镔���j�������̂Łu���r�i�K�v�̖��O�������B
�O�Ԑ��́u���̏o�Ђ����v�ɂ͑�ʂ̃��r�i�K�z�����h�J������炵�Ă���A�����ɗ��肢���ς��ɏW�߂邱�Ƃ��ł���B
�܂����̒��ɓ���Ȃ��Ă���݂̏�ɂ�������̂ŁA�����Ȏq���ł��ȒP�ɕ߂܂��邱�Ƃ��ł���B
�@�ŋ߂̓����p���h�J���ƊE�S�̂Ɍ����邱�Ƃ����A�Z�݂��ƂȂ�L�k���s�����Ă���炵���B
���̂��ߌ������芄�ꂽ�肵���s�Ǖ����ɓ������Ă��郄�h�J�������Ȃ��Ȃ��B
�@�T�����@�@���A�x����������
 �@�u�T�����̂悤�ȏ����ɂ͋C������v�Ƃ������t�������Ƃ����邩������Ȃ��B
�T�����̓L���C�ȊO�������Ă��邪�������^�����Ȗ��ŕ���ꂨ��A��������]���āu�T�����̂悤�ȁv�Ƃ������t�́u�������v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���邱�Ƃ�����B
�Y���̓T�����ނ肪����ŁA�u�Y���ޖ@�v�Ƃ����Ǝ��̒ނ�������݂��A�ނ�̍Ő������}����9�`11���̓��̏o�A���{�̊C�݂͔M���I�ȃT�����X�g�����ł���������Ă���B
��y�ɒނ�A�����ǂ��J���₷���A�����Ă����̂�����Ȃ��T�����ނ�͊Ǘ��l����D���ł���B
�@�u�T�����̂悤�ȏ����ɂ͋C������v�Ƃ������t�������Ƃ����邩������Ȃ��B
�T�����̓L���C�ȊO�������Ă��邪�������^�����Ȗ��ŕ���ꂨ��A��������]���āu�T�����̂悤�ȁv�Ƃ������t�́u�������v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���邱�Ƃ�����B
�Y���̓T�����ނ肪����ŁA�u�Y���ޖ@�v�Ƃ����Ǝ��̒ނ�������݂��A�ނ�̍Ő������}����9�`11���̓��̏o�A���{�̊C�݂͔M���I�ȃT�����X�g�����ł���������Ă���B
��y�ɒނ�A�����ǂ��J���₷���A�����Ă����̂�����Ȃ��T�����ނ�͊Ǘ��l����D���ł���B
�@�T�����́u���ꑔ�i�Ȃ�����@�C�ʂ�Y���C���̂����܂�j�v�ɗ����Y�ݕt����̂����A���̍ۊC���ɓ˂��h�����Đg���������Ȃ��Ȃ莀��ł��܂��T���������Ȃ��Ȃ��炵���B
�@�A�~���n�M�@�@���A�x����������
 �@�Ǘ��l���C�ɓ���̋��B�ő�ł�7cm���炢�ɂ����Ȃ�Ȃ����^�̃J���n�M�B���Ăɋ���̉͌��ʼn��C�Ȃ��C����Ԃł�����������R�̂ꂽ�B
�����̂ɂȂ��Ȃ���Ԃ̂����鋛�ŁA��������Ƃ����ɑ����Ď���ł��܂������ɁA�����ɓ��ꂽ����̍��͗Ⓚ�̐��G�T���n�V�ł܂�ł����Ȃ��ƐH�ׂ��A
���̂��߉Ƃ̗Ⓚ�ɂƐ���������������X���������������B
�C��(�A�}���Ȃ�)�Ɍ��ł��܂��ĐQ��Ƃ����K��������A�Ǘ��l�����̃V�[�����������A�����̒��ő̂��E�֍��U���Ȃ�����A
�����ĊC���𗣂��Ȃ����̃A�S�̋����Ɛ_�o�̐}�����ɂ͋��������̂��B���i�͉��₩�ŁA�����C�ォ������Ȃ��B
���Ȃ݂ɂ��̐����ɂ���̂̓I�X�ƃ��X�ŁA�I�X�̔��т�̂����ɂ͑����т����������Ă���B
�@�Ǘ��l���C�ɓ���̋��B�ő�ł�7cm���炢�ɂ����Ȃ�Ȃ����^�̃J���n�M�B���Ăɋ���̉͌��ʼn��C�Ȃ��C����Ԃł�����������R�̂ꂽ�B
�����̂ɂȂ��Ȃ���Ԃ̂����鋛�ŁA��������Ƃ����ɑ����Ď���ł��܂������ɁA�����ɓ��ꂽ����̍��͗Ⓚ�̐��G�T���n�V�ł܂�ł����Ȃ��ƐH�ׂ��A
���̂��߉Ƃ̗Ⓚ�ɂƐ���������������X���������������B
�C��(�A�}���Ȃ�)�Ɍ��ł��܂��ĐQ��Ƃ����K��������A�Ǘ��l�����̃V�[�����������A�����̒��ő̂��E�֍��U���Ȃ�����A
�����ĊC���𗣂��Ȃ����̃A�S�̋����Ɛ_�o�̐}�����ɂ͋��������̂��B���i�͉��₩�ŁA�����C�ォ������Ȃ��B
���Ȃ݂ɂ��̐����ɂ���̂̓I�X�ƃ��X�ŁA�I�X�̔��т�̂����ɂ͑����т����������Ă���B
�@�A�S�n�[�@�@���A�x����������
 �@�u�{�P���Ƃ����v�Ƃ������t�����������B���܂蓮�����A�悭�����̃J�x���ɒ���t���Ă����Ƃ��Ă���B
���̎p�ɃI�b�T���L�����o����̂͊Ǘ��l�������낤���B���i�͉��₩�ő��̋��̃P���J���邱�Ƃ����Ȃ����A�H���Ɋւ��Ă͂ǂ�~�ŁA
�����̑̂̔��������낤���Ƃ����l�������C�Ŋۂ݂̂ɂ���B�܂����Ȃ�^�t�ȋ��Ő����≖���̕ω��ɋ����A
�O�Ԑ��ł���݂̏�ɂł������[��5cm���Ȃ��悤�Ȑ����܂�̒��ł悭�ڂɂ���B
�@�u�{�P���Ƃ����v�Ƃ������t�����������B���܂蓮�����A�悭�����̃J�x���ɒ���t���Ă����Ƃ��Ă���B
���̎p�ɃI�b�T���L�����o����̂͊Ǘ��l�������낤���B���i�͉��₩�ő��̋��̃P���J���邱�Ƃ����Ȃ����A�H���Ɋւ��Ă͂ǂ�~�ŁA
�����̑̂̔��������낤���Ƃ����l�������C�Ŋۂ݂̂ɂ���B�܂����Ȃ�^�t�ȋ��Ő����≖���̕ω��ɋ����A
�O�Ԑ��ł���݂̏�ɂł������[��5cm���Ȃ��悤�Ȑ����܂�̒��ł悭�ڂɂ���B
�@�n�[�ނ�̊O���Ƃ��āA�u�_�{�n�[�v�ƌĂ�鋛���̂Q�i�_�{�n�[�Ƃ������͂��Ȃ��j�B
�܂��A�S�n�[�̓h�����Ƃ������Ǝp�����Ɏ��Ă���A�A�S�n�[�ƃh�����̈Ⴂ������悤�ɂȂ�ƁA�n�[�ނ�̍ۃh���炪�ł��邱�ƊԈႢ�Ȃ��B
�@�X�Y�L�@�@���A�x����������
 �@�ނ�l����D���ȋ����̂R�B�傫�Ȍ��ŋ���G�r�A�J�j�Ȃǂ�ߐH����T�^�I�ȓ��H���B
����ȏK������֓��ł̓��A�[�t�B�b�V���O�̑Ώۋ��Ƃ��Đ��Ȑl�C���ւ�A���̒ނ�ƊE�������Ă���̂͂��̋��̂��A�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ���������Ȃ��B
�����p�͐��E��X�Y�L�̂���C�Ƃ��Ēm���A���N�����p�ł�2000�g���ȏ�̃X�Y�L�����g������Ă���B
�܂��䂪��t���͋��l�ʓ��{��ŁA���ׂ̑D���s�ł̓u�����h���Ƃ��Ă�����o����Ă���B
�@�ނ�l����D���ȋ����̂R�B�傫�Ȍ��ŋ���G�r�A�J�j�Ȃǂ�ߐH����T�^�I�ȓ��H���B
����ȏK������֓��ł̓��A�[�t�B�b�V���O�̑Ώۋ��Ƃ��Đ��Ȑl�C���ւ�A���̒ނ�ƊE�������Ă���̂͂��̋��̂��A�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ���������Ȃ��B
�����p�͐��E��X�Y�L�̂���C�Ƃ��Ēm���A���N�����p�ł�2000�g���ȏ�̃X�Y�L�����g������Ă���B
�܂��䂪��t���͋��l�ʓ��{��ŁA���ׂ̑D���s�ł̓u�����h���Ƃ��Ă�����o����Ă���B
�@�t�ɂȂ�ƎO�Ԑ��ł͂�������̃X�Y�L�̒t����ڂɂ��邱�Ƃ��ł���B
�O�Ԑ��̐ĊO�G�����Ȃ����ƖL�x�ȃG�T���A���E��̓����p�̃X�Y�L�������x���Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B
���Ȃ݂ɎO�Ԑ��̃X�Y�L�����Ȃ�����B�ނ����炷���Ɋ������߂ƌ��������s���A��₵�����Ȃ��悤�Ɏ����A�낤�B
�@�A�J�G�C�@�@���A�x����������
 �@�ʖ��u�����̒n���v�B�O�Ԑ��ɂ������̃A�J�G�C���������A�Ăɒ����������O�Ԑ��ł̓A�J�G�C������ł����Ǝv����傫�ȃN���[�^�[��̍��̂��ڂ݂𑽐��݂邱�Ƃ��ł���B
���̒��Ԃɋ��͂ȓŐj�������Ă���h�����Ɣ��Ɋ댯�ŁA���E��L���ȃI�[�X�g�����A�l�Ƃ��Ēm����g�N���R�_�C���E�n���^�[�h�X�e�B�[�u�E�A�[�E�B������
���ɓŐj���Ď��S�������̂͂��܂�ɂ��L���B
���������炪�߂Â����蓥��Â����肵�Ȃ���Ύh����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�����ł̓X�����œ�������A�C���_�Ŋm�F���Ȃ���ړ�����̂��ǂ����낤�B
�@�ʖ��u�����̒n���v�B�O�Ԑ��ɂ������̃A�J�G�C���������A�Ăɒ����������O�Ԑ��ł̓A�J�G�C������ł����Ǝv����傫�ȃN���[�^�[��̍��̂��ڂ݂𑽐��݂邱�Ƃ��ł���B
���̒��Ԃɋ��͂ȓŐj�������Ă���h�����Ɣ��Ɋ댯�ŁA���E��L���ȃI�[�X�g�����A�l�Ƃ��Ēm����g�N���R�_�C���E�n���^�[�h�X�e�B�[�u�E�A�[�E�B������
���ɓŐj���Ď��S�������̂͂��܂�ɂ��L���B
���������炪�߂Â����蓥��Â����肵�Ȃ���Ύh����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�����ł̓X�����œ�������A�C���_�Ŋm�F���Ȃ���ړ�����̂��ǂ����낤�B
�@��������Ƃ��������Ŏ|��������A�����ڂ̃O���e�X�N���≺�����̖ʓ|�����������Ȃ�ǂ��H�ށB�h�g�ł��H�ׂ邱�Ƃ��ł���B
�@�C�V�K�j�@�@���A�x����������
 �r���L�����20cm�ɂ��Ȃ��^�̃J�j�B���i�͔��ɂǂ��҂Ōl�I�ɂ͎O�Ԑ��̃P���J�Ԓ����Ǝv���Ă���B�n�T�~�̗͎͂O�Ԑ��ŋ��N���X�Ŏw�����܂��Ɨ������邱�Ƃ��B
�����𐅑��ɕ�������Ŋ��A������J�j�A�L�܂ł���Ƃ����鐶����H���s�����Ă��܂��\�N�B
�r���L�����20cm�ɂ��Ȃ��^�̃J�j�B���i�͔��ɂǂ��҂Ōl�I�ɂ͎O�Ԑ��̃P���J�Ԓ����Ǝv���Ă���B�n�T�~�̗͎͂O�Ԑ��ŋ��N���X�Ŏw�����܂��Ɨ������邱�Ƃ��B
�����𐅑��ɕ�������Ŋ��A������J�j�A�L�܂ł���Ƃ����鐶����H���s�����Ă��܂��\�N�B
�@���ā`�H�ɂ����ĎO�Ԑ��ł͔�r�I�悭�ڂɂ���J�j�ŁA���̓�����A�����a�ɂ��āg�J�j�ԁh�⌊�ނ������Ə��S�҂ł���������Ƃ��B
���͖����ƂĂ��ǂ��A���X�`�̂ق���^�������K�j�ɂ���Ɛ�i�i�k�����ɍd���H�ׂÂ炢���j�B
�ŋ߂ł̓V�[�Y���ɂȂ�ƃC�V�K�j��ߊl���邽�߂ɑ吨�̊O���l���V�Y����K��A��ʂ̃C�V�K�j�����l���Ă������̗l�q�͉Ă̕������ƂȂ��Ă���c�����B
���ʐ^�́A7���Ɂg�J�j�ԁh�ŕߊl�����C�V�K�j�B�������H�ׂ邽�߁B
�@�}���R�u�V�K�j�@�@���A�x����������
 �@�J�j�̂����Ɂg�O�ɕ����h���Ƃ��ł���B�傫����2�`3cm�قǂ̏����ȃJ�j�B
�O�Ԑ��ł͏��ā`�Ăɂ悭�ڂɂ��邱�Ƃ��ł��邪�A���i�͍��ɔ��������Ă��邱�Ƃ��������߁A�̏W�ɂ̓R�c������B
�����j�b�p�[�̂悤�ȃn�T�~�����Ɏg���A�A�T���Ȃǂ�2���L�̂���������J���ĐH�ׂ�B
�@�J�j�̂����Ɂg�O�ɕ����h���Ƃ��ł���B�傫����2�`3cm�قǂ̏����ȃJ�j�B
�O�Ԑ��ł͏��ā`�Ăɂ悭�ڂɂ��邱�Ƃ��ł��邪�A���i�͍��ɔ��������Ă��邱�Ƃ��������߁A�̏W�ɂ̓R�c������B
�����j�b�p�[�̂悤�ȃn�T�~�����Ɏg���A�A�T���Ȃǂ�2���L�̂���������J���ĐH�ׂ�B
�@�P�C�̃}���R�u�V�K�j�̏�ɂ����P�C������Ă���p���悭�ڂɂ��邪�A����̓I�X�����X����납����������邱�Ƃɂ���āA���X��ʂ̃I�X�Ɏ���Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂��B
����͌���̑O��ɍs����̂Łu����O�i��j�K�[�h�v�Ƃ����B�����j�Ƃ��Ă��̃I���I�����Ղ�������͌��K���������̂ł���B
�O�Ԑ������ɓ������̂��鐶����
�@�J���C�̒t��
 �ƂĂ���肭���ɂ�����Ă���B������ꂽ��Ȃ��Ȃ��������B
�ƂĂ���肭���ɂ�����Ă���B������ꂽ��Ȃ��Ȃ��������B
�@�`�`�u
 �ƂĂ��^�t�ȋ��B��̂����Ō�܂Ő����c��B
�ƂĂ��^�t�ȋ��B��̂����Ō�܂Ő����c��B
�@�M���|�̒���
 �₩����C�����̒��ɂ������̂��D���B
�₩����C�����̒��ɂ������̂��D���B
�@�C�\�M���|
 2�{�̃c�m���g���[�h�}�[�N�B�A�C�h���I���݁B�������ɂ�炸���Ȃ�^�t�ȋ��B
2�{�̃c�m���g���[�h�}�[�N�B�A�C�h���I���݁B�������ɂ�炸���Ȃ�^�t�ȋ��B
�@�A�S�n�[
 �n���ȃ��c�B���Ђ�����Ԃ��Ƃ悭������B
�n���ȃ��c�B���Ђ�����Ԃ��Ƃ悭������B
�@�~�~�Y�n�[
 �n���ȃ��c�B���Ђ�����Ԃ��Ƃ悭������B
�n���ȃ��c�B���Ђ�����Ԃ��Ƃ悭������B
�@�{���̒t��
 80cm���炢�܂Ő�������B�t���͎キ�����₹��̂ŁA�a�����܂߂ɂ����邱�ƁB
80cm���炢�܂Ő�������B�t���͎キ�����₹��̂ŁA�a�����܂߂ɂ����邱�ƁB
�@���o���̒t��
 �����������͂��킢�����A�����Ƀf�J���Ȃ�B�f�J���Ȃ�Ƒ��̐������悭�H�ׂ�B
�����������͂��킢�����A�����Ƀf�J���Ȃ�B�f�J���Ȃ�Ƒ��̐������悭�H�ׂ�B
�@���o��
 �ڂ��ƂĂ��ǂ��B�������G�r����D���B
�ڂ��ƂĂ��ǂ��B�������G�r����D���B
�@���W�i
 �ƂĂ��C�������B���̋��������߂邱�Ƃ��B
�ƂĂ��C�������B���̋��������߂邱�Ƃ��B
�@�X�W�G�r�̒���
 �G�r�͎�ނ���������̂�����B�E�E�E�B
�G�r�͎�ނ���������̂�����B�E�E�E�B
�@���r�i�K�z�����h�J��
 �ŋ߂͊L����s���ʼnƒT������ς炵���B
�ŋ߂͊L����s���ʼnƒT������ς炵���B
�@�C�V�K�j
 ���^���K�j�̒��Ԃʼnj�����Ƃ��ł���B�n�T�~�̗͎͂O�Ԑ��ŋ��B�P���J�Ԓ��B
���^���K�j�̒��Ԃʼnj�����Ƃ��ł���B�n�T�~�̗͎͂O�Ԑ��ŋ��B�P���J�Ԓ��B
�@�C�\�K�j
 ���̃V�}�������B�P���J�������B
���̃V�}�������B�P���J�������B
�@�P�t�T�C�\�K�j
 �n�T�~�̂Ƃ���ɖт��͂��Ă���̂Łu�P�t�T�v�B�������P���J�������B
�n�T�~�̂Ƃ���ɖт��͂��Ă���̂Łu�P�t�T�v�B�������P���J�������B
�@�q���C�\�K�j
 �����Z��������������B
�����Z��������������B
�@�}�K�L
 ��[������ƊL����������J���Čċz���Ă���B�O�Ԑ��̃J�L�͔������炵���B
��[������ƊL����������J���Čċz���Ă���B�O�Ԑ��̃J�L�͔������炵���B
�@�A�J�j�V
 ���̊L���P���ĐH�ׂ�B�����͍��̒��ɂ���B�����ǂ��A�T�U�G�̑�p�i�ɂȂ�B
���̊L���P���ĐH�ׂ�B�����͍��̒��ɂ���B�����ǂ��A�T�U�G�̑�p�i�ɂȂ�B
�@�����T�L�C�K�C
 ������u���[���L�v�B�N���_�C�ނ�̃G�T�ɂ悭�g����B
������u���[���L�v�B�N���_�C�ނ�̃G�T�ɂ悭�g����B
�@�V���{��
 2�̌��Ő����z������f�����肵�Ă���B
2�̌��Ő����z������f�����肵�Ă���B
�@�^�e�W�}�C�\�M���`���N
 �I�����W�̃X�g���C�v�͗l���������B
�I�����W�̃X�g���C�v�͗l���������B
�@�}�i�}�R
 ���̒��̃G�T��H�ׂ�B�{�C���o���͓̂~�B
���̒��̃G�T��H�ׂ�B�{�C���o���͓̂~�B
�O�Ԑ������}��
�@�A�i�S�i�}�A�i�S�j
![]() �����p�ł͕x�É��ƉH�c�����L���ȋ���ł����A�O�Ԑ��ł����������܂��B��s���Ȃ��߁A���̐����Ŏp������킷�̂͂܂�ł����A�Ƃ����܃J�L�k�̒������������܂��B�i�ȁj
�����p�ł͕x�É��ƉH�c�����L���ȋ���ł����A�O�Ԑ��ł����������܂��B��s���Ȃ��߁A���̐����Ŏp������킷�̂͂܂�ł����A�Ƃ����܃J�L�k�̒������������܂��B�i�ȁj
�@�A���t���V
 �܂��L�̒��ԂŁA�̓��ɑމ������L�k�������Ă��āA�A�I�T�Ȃǂ̊C����H�ׂ܂��B���O�̗R���́A�C�����Ŏ��F�̉t���o���A���ꂪ�J�_�̂悤�ɍL���邩�炾�����ł��B���݂����Ƃ������Ă��܂��B�i�܁j
�܂��L�̒��ԂŁA�̓��ɑމ������L�k�������Ă��āA�A�I�T�Ȃǂ̊C����H�ׂ܂��B���O�̗R���́A�C�����Ŏ��F�̉t���o���A���ꂪ�J�_�̂悤�ɍL���邩�炾�����ł��B���݂����Ƃ������Ă��܂��B�i�܁j
�@�A���t���V�̗�
 �e�A���t���V�́A�ꌩ�i���N�W�ł����A���L�̒��ԂŁA�މ������L�k���̓��ɂ���܂��B ���̗���́A�܂�Ń��[�����̂悤�ŁA�u�C�����߂�v�ƌ����Ă���A�O�Ԑ��ł����܂ɂ݂����܂��B�i�܁j
�e�A���t���V�́A�ꌩ�i���N�W�ł����A���L�̒��ԂŁA�މ������L�k���̓��ɂ���܂��B ���̗���́A�܂�Ń��[�����̂悤�ŁA�u�C�����߂�v�ƌ����Ă���A�O�Ԑ��ł����܂ɂ݂����܂��B�i�܁j
�@�C�\�M���`���N
 �w�ł����ƐG�����Ă܂邭�Ȃ�܂��B �O�Ԑ��ɂ́A�C�V���P�C�\�M���`���N��N���K�l�C�\�M���`���N�Ƃ��������킪����悤�ł����A �ڂ������Ƃ͂킩���Ă��Ȃ��悤�ł��B
�w�ł����ƐG�����Ă܂邭�Ȃ�܂��B �O�Ԑ��ɂ́A�C�V���P�C�\�M���`���N��N���K�l�C�\�M���`���N�Ƃ��������킪����悤�ł����A �ڂ������Ƃ͂킩���Ă��Ȃ��悤�ł��B
�@�C�_�e���M���|
 ��̉A��A�J�L�̊k�̒��Ȃǂ̈Â��Ƃ��낪�D�݂ŁA�����ȃG�r��S�J�C��H�ׂ܂��B �u����ہv�́A�����ȕ��r�����P��������܂��A�u�����Ă�ہv�ɂ�2����܂��B�̂̑��ʂ̑O�����ɂ͍����c�������{����܂��B���܂��ƒɂ��̂Œ��ӂ��K�v�B
��̉A��A�J�L�̊k�̒��Ȃǂ̈Â��Ƃ��낪�D�݂ŁA�����ȃG�r��S�J�C��H�ׂ܂��B �u����ہv�́A�����ȕ��r�����P��������܂��A�u�����Ă�ہv�ɂ�2����܂��B�̂̑��ʂ̑O�����ɂ͍����c�������{����܂��B���܂��ƒɂ��̂Œ��ӂ��K�v�B
�@�C�b�J�N�N���K�j
 �{���̕��z�n�́A�k�Ă̑����m���݂ł����A�D�̃o���X�g���ɂ���āA1970�N����A���{�ɓ���܂����B������O����ł��B�Ȋ��ł��A�������т邱�Ƃ��o����̂ō���S���K�͂Œ蒅���Ă��܂��B�傫����2cm�قǁB�Ƃ��Ă����킢���ł��B�i�܁j
�{���̕��z�n�́A�k�Ă̑����m���݂ł����A�D�̃o���X�g���ɂ���āA1970�N����A���{�ɓ���܂����B������O����ł��B�Ȋ��ł��A�������т邱�Ƃ��o����̂ō���S���K�͂Œ蒅���Ă��܂��B�傫����2cm�قǁB�Ƃ��Ă����킢���ł��B�i�܁j
�@�C�{�j�V
 �O�Ԑ��Ń|�s�����[�ɂ݂��銪�L�̒��ԁB�L�Ȃǂ����ׂ܂��B
�O�Ԑ��Ń|�s�����[�ɂ݂��銪�L�̒��ԁB�L�Ȃǂ����ׂ܂��B
�������ł̓K���X�ɂ������Ĉړ�����p�������܂��B�J�L�k�ȂǂɃr�b�V���Ɨ����Y�݂����Ă��܂��i�܁j
�@�J�C����
�\�ʂɂ��鏬���ȍE����A���V����H�����h�߂��邱�ƂŕߐH���邽�߁A���������� �����ƂȂ鐅���̔�������L�@������������������ʂ����Ă��܂��B���������Ђ������Ȃ����߁A�X�|���W�Ƃ��ėp�����Ă��܂��B�i�܁j
�@�J���U�V�S�J�C�̒���
 �����p����тł݂���B �ݕǁA�L�k�A��ȂǂɁA�ΊD���̃p�C�v�\���� ���ǂ�����ɕt�����Ă��܂��B �G����o���āA�v�����N�g�����h���Ƃ��ĐH�ׂĂ��܂��B�i�܁j
�����p����тł݂���B �ݕǁA�L�k�A��ȂǂɁA�ΊD���̃p�C�v�\���� ���ǂ�����ɕt�����Ă��܂��B �G����o���āA�v�����N�g�����h���Ƃ��ĐH�ׂĂ��܂��B�i�܁j
�@�M�}
 �w��1�{�A����2�{�̂Ƃ�������J���n�M�̒��Ԃł��B���āA������́u�ɓ������ȓ�v���邢�́u���{�����ȓ�v�Ƃ���Ă��܂������A�ߔN�A�O�Ԑ��ő������邱�Ƃ��ł��܂��B�i�ȁj
�w��1�{�A����2�{�̂Ƃ�������J���n�M�̒��Ԃł��B���āA������́u�ɓ������ȓ�v���邢�́u���{�����ȓ�v�Ƃ���Ă��܂������A�ߔN�A�O�Ԑ��ő������邱�Ƃ��ł��܂��B�i�ȁj
�@�V���I�E�M�K�j
 ��̌`�������̂ƁA�\�ʂ̃V���������ł��B��Ɋ�̊Ԃ�J�L�ʁi�J�L�̂����܂�j�Ȃǂɐ������Ă��܂��B�i�ȁj
��̌`�������̂ƁA�\�ʂ̃V���������ł��B��Ɋ�̊Ԃ�J�L�ʁi�J�L�̂����܂�j�Ȃǂɐ������Ă��܂��B�i�ȁj
�@�X�W�G�r�̒���
 �ԂŊȒP�Ɏ�邱�Ƃ��ł��܂����A�O�Ԑ��ɂ͂R��ވȏ�̃X�W�G�r�����܂��B�c�m�̕����Ō����������悤�ł�������ł��B
�ԂŊȒP�Ɏ�邱�Ƃ��ł��܂����A�O�Ԑ��ɂ͂R��ވȏ�̃X�W�G�r�����܂��B�c�m�̕����Ō����������悤�ł�������ł��B
���Ăɐ���ɎY�����A�ʐ^�̂悤�ɗ����������������X�W�G�r���悭�݂܂��B�i�܁j
�@�`�`�u
 �}�n�[�̊O���Ƃ��Ă��Ȃ��݂̃_�{�n�[�ł���B���ɂ���Ă悭�̐F��ω�������B �j���ɔ����_�Ƌ��h�t�����ɑя�̉��F����������B�D����̐̉����Q���̉��ɐ������A�G�H���ł���B5�`9�����Y�����ŁA�̉��Ȃǂɗ����Y�ށB
�}�n�[�̊O���Ƃ��Ă��Ȃ��݂̃_�{�n�[�ł���B���ɂ���Ă悭�̐F��ω�������B �j���ɔ����_�Ƌ��h�t�����ɑя�̉��F����������B�D����̐̉����Q���̉��ɐ������A�G�H���ł���B5�`9�����Y�����ŁA�̉��Ȃǂɗ����Y�ށB
�e�b�|�E�G�r�̒���
 �p�����gPistol�@Shrimp�h�̃e�b�|�E�G�r�B�Е��̃n�T�~���Ƃ��Ă��傫���̂������ł��B
�p�����gPistol�@Shrimp�h�̃e�b�|�E�G�r�B�Е��̃n�T�~���Ƃ��Ă��傫���̂������ł��B
���̃n�T�~�Łu�p�`���b�I�v�Ƒ傫�ȉ����o���A�߂Â��Ă����V�G���Њd������A�����ƂȂ鐶�������������ċC�₳�����肷������ł���B���܂��ƕ������邩�ȁH�i�܁j
�@�g�T�J�M���|
 �V�}�V�}�͗l�������I�ȃM���|�̒��ԁB�J�L�k�̊Ԃɓ����Ă��邱�Ƃ��������߁A���i�͂Ȃ��Ȃ��A���̎p���݂邱�Ƃ͂ł��܂���B�u�g�T�J�v������̂́A�I�X�����ł��B���X���J�L�k�̂Ȃ��ɗ����Y�ނƁA�I�X�͊k�̒��ɓ����āA�ꐶ�������܂��B�i�܁j
�V�}�V�}�͗l�������I�ȃM���|�̒��ԁB�J�L�k�̊Ԃɓ����Ă��邱�Ƃ��������߁A���i�͂Ȃ��Ȃ��A���̎p���݂邱�Ƃ͂ł��܂���B�u�g�T�J�v������̂́A�I�X�����ł��B���X���J�L�k�̂Ȃ��ɗ����Y�ނƁA�I�X�͊k�̒��ɓ����āA�ꐶ�������܂��B�i�܁j
�@�}�K�L
 �@
�H�p�ɂȂ�A�����p���p�ɍL�����z���Ă��܂��B�����p�p�����ł͒��ԑт���ɂ����Đ������A����ȃJ�L�ʂ��`������A�����Ƃ̊k�������̐������̐��݂��Ƃ��Ė𗧂��Ă��܂��B�v�����N�g����H�ׁA����2���L���l�A�C���̏�@�\�����ڂ���Ă��܂��B
�@
�H�p�ɂȂ�A�����p���p�ɍL�����z���Ă��܂��B�����p�p�����ł͒��ԑт���ɂ����Đ������A����ȃJ�L�ʂ��`������A�����Ƃ̊k�������̐������̐��݂��Ƃ��Ė𗧂��Ă��܂��B�v�����N�g����H�ׁA����2���L���l�A�C���̏�@�\�����ڂ���Ă��܂��B
�@�}�c�_�C
 �g�����C�ɐ������鋛�ŁA���������1��������H���ł��B�t���͌͂�t�ɋ[�Ԃ��Đg�����܂��B�O�Ԑ��ɂ͒g���ɏ���ė�����Ă����Ǝv���܂��B�i�ȁj
�g�����C�ɐ������鋛�ŁA���������1��������H���ł��B�t���͌͂�t�ɋ[�Ԃ��Đg�����܂��B�O�Ԑ��ɂ͒g���ɏ���ė�����Ă����Ǝv���܂��B�i�ȁj
�@�}�n�[
 �̑��Ƀ��U�C�N�̂悤�Ɋ��F�����Ȃ�сA�w�т����т�ɂ��������_���Ȃ��ł���B ���Ă���H�ɂ����ĉ͌��⊱���̐ɂ��邪�A������������A�ӏH�ɂ͐[��Ɉړ����Y������B��ɃS�J�C�Ȃǂ̒ꐶ�������a�Ƃ���B
�̑��Ƀ��U�C�N�̂悤�Ɋ��F�����Ȃ�сA�w�т����т�ɂ��������_���Ȃ��ł���B ���Ă���H�ɂ����ĉ͌��⊱���̐ɂ��邪�A������������A�ӏH�ɂ͐[��Ɉړ����Y������B��ɃS�J�C�Ȃǂ̒ꐶ�������a�Ƃ���B
�@�}�i�}�R
 �ŋ߂ł͍����_�C�A�����h�H�ȂnjĂ�� ����i�}�R�A�l�X�ȐF�̃i�}�R�����܂��B �����ɂ���C�{�C�{�́A�q�g�f�ȂǂƋ��ʂ� ������u�Ǒ��v�Ƃ������ł��B
���D�����O���O�H�ׂėL�@�����z�����A �c��̍��D��r�����܂��B�i�܁j
�ŋ߂ł͍����_�C�A�����h�H�ȂnjĂ�� ����i�}�R�A�l�X�ȐF�̃i�}�R�����܂��B �����ɂ���C�{�C�{�́A�q�g�f�ȂǂƋ��ʂ� ������u�Ǒ��v�Ƃ������ł��B
���D�����O���O�H�ׂėL�@�����z�����A �c��̍��D��r�����܂��B�i�܁j
�@�}���R�u�V�K�j
 �J�j�Ȃ̂ɁA�O��ɕ������Ƃ��ł��܂��B���̃J�j�Ɣ�ׂāA�܂�������E���킢�������������Ă��܂��B �T�����L�����N�^�[�ɂȂ��Ă��܂��B
�J�j�Ȃ̂ɁA�O��ɕ������Ƃ��ł��܂��B���̃J�j�Ɣ�ׂāA�܂�������E���킢�������������Ă��܂��B �T�����L�����N�^�[�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�����T�L�C�K�C
�t�����X�����Ɏg����C�K�C�̒��ԁB���[���L�Ƃ������O�̂ق����L���ł��傤���B �D�ʼn^�ꂽ���̂���݂�`�ő�ʂɔɐB���A���̌�A�����ɂȂ�����܂����BIUCN�i���ێ��R�ی�A���j�̐��E�̐N���I�O���탏�[�X�g100�Ɏw�肳��Ă��܂��B�i�n�j
�@���r�i�K�z�����h�J��
 ���n�����邭�̂ɓK�����������������Ă��܂��B������C����H�ׁA�����̏Ɉ���Ă��܂��B�O�Ԑ��ł͑�R�����鐶������1�ł��B�i���j
���n�����邭�̂ɓK�����������������Ă��܂��B������C����H�ׁA�����̏Ɉ���Ă��܂��B�O�Ԑ��ł͑�R�����鐶������1�ł��B�i���j
�@�������́F�Y�����R�܂邲�ƒT����

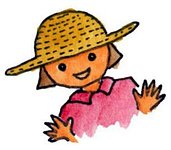
�Y���O�Ԑ����ɂ����
��279-0012
��t���Y���s���D2-3-303
TEL �O�S�V�|�R�T�R�|�W�P�R�S�i���R�j